司法書士試験の難易度はどれくらいなのでしょうか?
毎年多くの人が挑戦する司法書士試験ですが、合格率はわずか数%。法律系の国家資格の中でも難関と言われています。
本記事では、最新の合格率をもとに試験の実態を紹介するとともに、実際に勉強を始めた人がぶつかる「3つの壁」についても詳しく解説します。
これから司法書士を目指す方や、勉強を始めたばかりの方にとって、試験の全体像や乗り越えるべきポイントが見えてくるはずです。
司法書士試験の合格率はどれくらい?
司法書士試験の合格率をご存じでしょうか?
令和6年度(2024年)のデータでは、
**合格率は5.3%**でした。
-
出願者数:16,837人
-
実際の受験者数:13,960人
-
合格者数:737人
こうして数字を見ると、出願したものの実際には受験しなかった人が約3,000人いることが分かります。
司法書士試験は、学歴や年齢に関係なく、誰でも受験できる国家試験です。
そのため、受験者の本気度にはかなり差があり、全員が本気で合格を目指しているとは限りません。
実際に「司法書士になりたい!」と強い意志を持って受験している人は、おそらく全体の10〜20%程度ではないかと感じています。
つまり、この本気の層の中で上位の成績を取ることができれば、合格は十分に目指せるということになります。
近年は受験者数が減少傾向にあり、それに伴って合格率も少しずつ上がってきました。以前は合格率が3%台だった時期もあるので、5.3%という数字はやや高くなってきた印象です。とはいえ、やはり狭き門であることに変わりはありません。
ですが、逆に言えば「きちんと対策をすれば合格できる試験」でもあります。
本気で司法書士を目指すのであれば、計画的に勉強を積み重ねることで、合格は決して夢ではありません。
司法書士試験の勉強で立ちはだかる「3つの壁」
テキストを一周する壁
司法書士試験には、なんと11科目もあります。
まず最初の大きな壁は、全科目を一通り終わらせることです。
つまり、
-
テキストを一周読み切る
-
講義を最後まで受ける
-
過去問を全体的に回してみる
といった作業を、すべての科目についてこなす必要があります。
しかしこれが想像以上に大変です。
講義だけでも膨大な時間がかかりますし、独学の場合は分からない部分を抱えながらも、まず一周読み進めなければなりません。
この**「最初の一周」**を完走できずに挫折してしまう人も、実際にはかなり多いです。
ですから、全科目を一通り終えられただけでも、かなり勉強が進んだと言えるのです。
基準点を突破する壁
司法書士試験は、
-
択一式(マークシート)
-
記述式
の2つで構成されていますが、まず択一式には**「基準点」**という関門があります。
これは、一定の点数を取れていないと、その時点で不合格になるという制度です。
たとえ一部の科目で満点を取っていても、他の科目で基準点を下回っていれば記述式の採点すらしてもらえません。
毎年、約13,000人が受験しますが、この基準点を超えられるのはおよそ2,000人程度と言われています。
つまり、この基準点を突破するだけで、上位15%ほどに入ることになり、合格に一気に近づけるということです。
基準点突破後、さらに点を積み上げる壁
とはいえ、基準点を突破するだけでは合格できません。
たとえば、基準点を超えた2,000人のうち、実際の合格者は600〜700人程度。
つまり、残りの1,300〜1,400人は不合格となってしまうのです。
この段階に来ると、受験生のレベルも高く、実力も拮抗しています。
その中でさらに点数を積み上げていく必要があるため、合格を勝ち取るには一段と努力が求められます。
この「最後の壁」を越えられるかどうかが、合格・不合格の明暗を分ける大きなポイントになります。
まとめ・司法書士試験を受ける人に言いたいこと
司法書士試験は合格率役5%という、簡単ではない試験です。ですがこれに挑戦しようと思って勉強を始めた方は受かる資質はあると思います。
さらに11科目のテキストなどの勉強を一周回すことができたのなら、合格の可能性は高まっているし、基準点にまで達したのならあと一息です。
勉強は自分と向き合ってやるものなので、SNSなどで他の人が勉強の進み具合などを発信していても、「自分はそんなにできていない」などと落ち込むことはありません。勉強の進み具合は人それぞれ、勉強方法も人それぞれです。
ネット上の良くない影響を及ぼす情報は気にせずに、自分を信じてとにかく何週もテキストをやり込むことで合格に近づくことができるはずです。
司法書士は特別な才能や技術がなくても、学歴が無くても、年齢がいくつでも挑戦できる資格なので、是非頑張って挑戦してください。

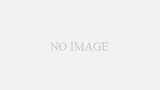
コメント