司法書士として独立開業を考えたとき、まず気になるのが「どれくらいお金がかかるのか」という点ではないでしょうか。私自身も開業にあたって真っ先に不安だったのが資金面でした。
開業資金は大きく分けて、事務所の設備や備品など初期に必要な「ハード面の費用」と、開業してすぐに収入が入るわけではないことを踏まえた「運転資金」の2つがあります。特に運転資金は、最低でも半年分は確保しておかないと、精神的にも経営的にも厳しくなります。
この記事では、自分の経験をもとに、独立開業に必要な資金とその内訳、そしてどんな準備が必要かをわかりやすくお伝えします。
設備でかかる費用
事務所物件の費用
まず最初に必要なのが、事務所を構えるための費用です。
開業にあたっては、「自宅開業」「事務所を借りる」「レンタルオフィスを利用する」といった選択肢がありますが、私としては自宅開業はおすすめしません。
自分が依頼者の立場になって考えると、自宅をオフィスにしている人よりも、きちんとした場所に事務所を構えている人の方が信頼できると思いませんか?
また、駅から近い・アクセスしやすい場所であれば、なおさら依頼しやすくなるはずです。ですので、なるべくオフィスを借りてスタートするのが理想的です。
物件を借りるには、立地や広さだけでなく初期費用も考えておく必要があります。
テナント物件では、敷金・礼金だけで家賃の10か月〜1年分が必要になることも珍しくありません。たとえば家賃が月50万円なら、それだけで500万円前後の費用がかかることもあります。さらに内装を整えようとすると、坪単価10万円以上の費用が発生することもあるため、注意が必要です。
ただし、開業当初はそこまでこだわらなくてOKです。
まずは最低限の環境でスタートしましょう。
都内でも狭い事務所なら家賃10~15万円程度で見つかります。
家賃は売上の10%程度に収めるのが理想なので、月10万円の家賃なら売上100万円を目指すという感覚です。
たとえば、家賃10万円の物件なら、敷金・礼金で60~100万円ほど。内装に費用をかけず、最低限の形でスタートするのが現実的です。
備品と通信環境を整える費用
次に必要なのが、業務に使う機器や通信環境の整備です。
インターネットがなければ仕事にならないので、まず通信インフラは必須です。
私の場合は、以下のような備品を揃えました:
-
パソコン(レンタルを利用)
-
ドットプリンター
-
複合機(コピー・FAX・スキャナー一体型)
-
周辺機器・事務用品
パソコンはリースではなくレンタルをおすすめします。長期契約の縛りが少なく、故障時の交換対応もスムーズだからです。
一部は中古品で揃えたこともあり、備品全体の費用は約50万円程度で収まりました。
ホームページ作成の費用
開業と同時にホームページは必ず用意しておくべきです。
今の時代、ホームページがない司法書士事務所はほぼ信頼されません。
開業日が決まっているなら、それまでにしっかり準備しておきましょう。
自分で作成できる方もいるかもしれませんが、集客を意識するならプロに依頼するのがベストです。
初期費用として30万〜50万円程度を見込んでおくと良いでしょう。将来的には内容の見直しやリニューアルを行っていくことになります。
運転資金はいくら必要?
独立開業の際に忘れてはいけないのが、「運転資金」の準備です。
初期設備費用とは別に、開業後しばらくは売上が安定しないことを想定して、日々の経費や生活費をしっかりカバーできるだけの資金を用意しておく必要があります。
一般的には、最低でも半年分の運転資金を確保しておくのが安心と言われています。
運転資金の内訳
まず、司法書士として活動を続けるには、毎月の司法書士会の会費が発生します。
この金額は地域によって差がありますが、おおよそ月25,000円〜30,000円程度が目安です。
半年分で計算すると、15万円〜18万円ほどの資金を確保しておく必要があります。
加えて、開業してすぐに売上が出るとは限りません。
開業から半年ほど無収入の期間が続く可能性もあります。
そのため、自分自身の生活費も運転資金に含めて考えておく必要があります。
例えば、毎月20万円の生活費が必要だとすると、半年で120万円が必要です。
このように、「司法書士会の会費」+「生活費」で、最低でも150万円前後の運転資金を見込んでおくと安心です。
営業経費・交際費
開業後に仕事を得るには、こちらから積極的に動いて「存在を知ってもらう」ことが不可欠です。
つまり、営業活動や人脈づくりのための費用も、運転資金に含めて考える必要があります。
具体的には以下のような費用が発生します:
-
名刺や会社案内などの制作費
-
開業の案内を送るためのDM費用
-
異業種交流会やセミナーへの参加費
-
紹介先やパートナーとの会食などの交際費
こうした費用は一つひとつは大きくなくても、積み重なるとそれなりの金額になります。
私の場合は、営業・交際費として毎月10万円程度の予算を見込み、半年分で60万円ほど確保しました。
もちろん、営業費用は「金額の多さ」よりも、「相手を大切にする気持ち」が伝わることの方が大切です。
ただし、名刺が雑だったり、第一印象が良くないと信頼に繋がりませんので、必要最低限の質にはこだわった方がいいと感じています。
独立して6か月・いくら必要?
司法書士として独立開業するにあたっては、初期投資としての設備費用と、売上が安定するまでの運転資金の2つをしっかり見積もる必要があります。
特に開業後の6か月間は収入が不安定、もしくはゼロの可能性もあるため、それを見越した資金準備が重要です。
まず、設備面の初期費用としては以下のような出費が想定されます:
-
事務所の敷金・礼金・家賃(狭い場所でスタートしても)…… 約100万円
-
備品・通信機器などの購入費用……………………………………… 約50万円
-
ホームページ作成費用………………………………………………… 約30万円
合計すると、初期費用として180万〜200万円程度が必要です。
次に、運転資金として用意しておきたいのが、
-
司法書士会の会費(半年分)……………………………………… 約18万円
-
自身の生活費(毎月20万円×6か月)…………………………… 約120万円
-
営業活動・交際費(毎月10万円×6か月)……………………… 約60万円
これらを合わせて、運転資金は200万円前後を想定しておくと安心です。
つまり、開業から半年間を安定して乗り切るためには、合計でおよそ400万円程度の資金が必要になります。
もちろん、事務所の場所や設備にどこまでお金をかけるかで金額は前後しますが、無理のない範囲で初期費用を抑えつつ、運転資金をしっかり確保することが成功のカギになります。
資金の調達
独立開業を目指す際に大きな課題となるのが、開業資金や運転資金をどうやって用意するかという点です。
まず基本となるのは自己資金です。できれば100万円から200万円程度は、自力で貯めておくことが望ましいです。これが開業の信頼性にもつながりますし、融資を受ける際の自己負担割合としても重要です。
それでも足りない場合は、公的機関や金融機関からの融資を検討しましょう。司法書士は国家資格であり、比較的信用力があるため、無担保・無保証で融資を受けられるケースもあります。特に「日本政策金融公庫」などは、創業支援に力を入れているため、司法書士の独立開業でも多く利用されています。
また、場合によっては両親や親族、信頼できる友人からの援助や借入れを検討するのも一つの選択肢です。気が引けるかもしれませんが、返済の計画をしっかり立てた上で誠意をもって相談すれば、力になってくれることもあるでしょう。
重要なのは、無理なく現実的に開業後6か月間を乗り切れるだけの資金をどう確保するかという視点で、複数の方法を組み合わせて調達することです。
まとめ
司法書士として独立開業するには、事務所の設備や備品、ホームページなどにかかる初期費用と、収入が安定するまでの生活費や営業費用といった運転資金の両方をしっかり準備しておく必要があります。
目安としては、設備投資に約200万円、運転資金として6か月分で100〜150万円ほど、合計で300〜350万円前後の資金を想定しておくと安心です。
資金の調達は、まずは自己資金を準備し、不足分は融資や家族の支援なども視野に入れながら現実的な計画を立てることが大切です。
最初は不安も多いかもしれませんが、しっかりと準備をすれば、開業後のスタートをスムーズに切ることができます。着実に一歩ずつ、信頼される事務所を目指していきましょう。

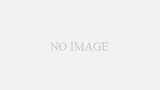

コメント