「司法書士って聞いたことはあるけど、具体的にどんな仕事をしているの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
司法書士は、法律の専門家として、登記業務や裁判所への書類作成、成年後見など、私たちの生活に密接に関わるさまざまな仕事をしています。
この記事では、司法書士の代表的な業務内容を、できるだけわかりやすくご紹介します。
「司法書士を目指そうかな」と考えている方にも、「単に興味がある」という方にも参考になる内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
司法書士の仕事
司法書士の主な仕事は、大きく分けて4つの分野に分かれます。
1、登記に関する仕事
-
不動産登記(家や土地を買ったときの名義変更など)
-
商業登記(会社の設立や役員変更など)
2、相続に関する仕事
-
相続手続き(相続人の調査や名義変更)
-
成年後見(判断能力の低下した高齢者などの支援)
-
家族信託(資産管理を家族に託す仕組みのサポート)
3、裁判に関する仕事
-
債務整理(借金の減額や返済方法の調整など)
※一定の条件を満たせば、簡易裁判所での代理業務も可能です。
4、その他の仕事
-
帰化申請の書類作成
-
法律相談や供託手続きなど
司法書士の役割は、「トラブルを未然に防ぐこと」にあります。
たとえば、登記や相続の手続きをきちんとしておかないと、後から大きな問題や争いにつながることもあります。
それでは、それぞれの内容について解説します。
不動産登記と商業登記とは?
司法書士が行う代表的な仕事の一つに、登記業務があります。
ここでは、不動産登記と商業登記について、わかりやすく解説していきます。
不動産登記とは?
たとえば、Aさんが持っている家をBさんに売ったとします。ところが、Aさんは同じ家をCさんにも売ってしまいました。
このとき、「本当の所有者は誰なのか?」という争いが起きる可能性がありますよね。
このようなトラブルを防ぐために必要なのが、不動産登記です。
不動産登記とは、土地や建物の所有者の情報を、法務局に正式に記録する手続きのこと。
そしてこの登記は、先に登記した人が優先されるというルールがあります。
つまり、もしBさんが先に登記をしていれば、「この家は私のものです」とCさんに対して主張できるのです。
司法書士は、不動産売買や相続、住宅ローンの完済など、不動産の名義変更が必要な場面で登記手続きをサポートします。
一般の人が司法書士と関わる場面
一般の方が司法書士と関わるのは、たとえばこんなときです:
-
マイホームを購入したとき
-
住宅ローンを完済したとき
-
親族が亡くなって相続が発生したとき
こういった場面で、司法書士が名義変更などの登記手続きを行います。
ただし、多くの人は司法書士に直接依頼する経験がありません。そのため通常は、銀行や不動産会社を通じて司法書士が紹介されることがほとんどです。
実際、多くの銀行や不動産会社は、提携している司法書士と継続的にやり取りしています。
そのため、司法書士として開業したばかりの人などは、銀行や不動産会社に営業をかけて関係を築き、仕事をもらえるよう働きかけるケースもあります。
不動産登記の現状
近年、不動産登記の件数は少しずつ減少しています。
これは、住宅の新築数がバブル期に比べて減っていることなどが影響しています。
その結果、登記の仕事をめぐる競争も激しくなっています。
最近では、全国展開している大手司法書士法人も増えてきており、大規模な不動産会社などでは、登記業務をまとめて法人に一括依頼するケースも増加中です。
それでも、不動産登記はトラブルを未然に防ぐ重要な業務であり、司法書士にとっては今も中心的な仕事のひとつです。
商業登記とは?
もう一つの主要業務が商業登記です。
商業登記とは、会社に関する情報を法務局に登録する手続きのことです。たとえば:
-
会社を設立する
-
会社の名前(商号)を変更する
-
本店を移転する
-
役員(社長や取締役)を変更する
といった場合には、必ず法務局に申請しなければなりません。
司法書士は、こうした手続きを代行したり、必要書類の作成をサポートしたりしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
このように、不動産登記も商業登記も、司法書士が日常の法律手続きの専門家として支えている分野です。
どちらも「正しく記録を残す」ことで、将来のトラブルを防ぐという大切な役割を担っています。
相続に関する仕事
司法書士が関わる仕事の中でも、相続に関する業務は年々重要性が増しています。
成年後見制度
相続分野で代表的なのが、成年後見制度です。
たとえば、認知症や障害などの理由で、本人が自分の財産を管理することが難しくなった場合に、代わりに財産管理や契約手続きを行う人を家庭裁判所が選任する制度です。
この「後見人」には、司法書士だけでなく、弁護士や社会福祉士などもなることができますが、実際には司法書士が後見人になるケースが多いのが現状です。特に、女性の司法書士が活躍しているケースも多く見られます。
最近注目の「家族信託」
近年では、「認知症になる前に備えておきたい」というニーズから、家族信託という仕組みが注目されています。
信託とは、財産の管理や運用を信頼できる家族などに託す仕組みのことで、本人が判断能力を失っても、あらかじめ定めたルールでスムーズに財産管理を行うことができます。
相続業務は「生前」と「死後」に分かれる
司法書士が関わる相続の仕事は、大きく分けると次の2つのタイミングで発生します。
● 生前の相続対策
-
遺言書の作成サポート
→ 遺言の内容を法的に有効な形に整えるお手伝いをします。 -
信託契約の組成支援
→ 将来の財産管理の計画を事前に整備します。
● 死後の相続手続き
-
不動産の名義変更(相続登記)
-
預貯金の解約や名義変更
-
相続人間の遺産分割協議書の作成支援
-
相続税に関する相談(税理士との連携)
これらの手続きは、複雑で負担の大きいものが多いため、司法書士が間に入ってサポートします。
多職種との連携がカギ
相続に関する手続きは、司法書士だけでは完結しないことが多いのが実情です。
-
相続人同士のトラブルがあれば → 弁護士
-
相続税の申告が必要なら → 税理士
-
不動産の売却が発生すれば → 不動産会社
といったように、様々な専門家との連携が必要になります。
このとき、最初の相談窓口(入り口)となるのが司法書士であることも少なくありません。
法律・登記・手続きに強い司法書士が、他士業や関係者と連携して、相続全体をスムーズに進めていく役割を果たしています。
裁判に関する仕事
司法書士は、登記や相続の専門家というイメージが強いかもしれませんが、裁判に関わる業務も一部認められています。
簡易裁判所での業務が可能に
2002年(平成14年)の法改正により、司法書士は簡易裁判所での代理権を持つことができるようになりました。
具体的には、140万円以下の民事事件に限り、司法書士が依頼者の代理人として裁判に関与することが可能になったのです。
この制度により、特に増えたのが債務整理の分野での司法書士の活躍です。
当時は、消費者金融などに対して過払い金返還請求の訴訟を行う司法書士も多くいました。
司法書士にできること・できないこと
司法書士が扱えるのは、**簡易裁判所の管轄に限られた事件(請求額140万円以下)**です。
たとえば、
-
任意整理の手続き
-
過払い金請求の代理
などは可能ですが、 -
自己破産
-
個人再生
といった手続きでは、司法書士は申立書の作成支援はできても、代理人になることはできません。
そのため、140万円を超える複雑な事件については、弁護士に依頼または紹介するケースが一般的です。
司法書士が扱えるその他のトラブル
法律上は、司法書士も以下のような民事事件に関与することができます。
-
交通事故の損害賠償請求
-
賃貸借契約のトラブル(家賃滞納など)
ただし、実際にはこうした裁判業務を積極的に行っている司法書士は多くはなく、あくまで一部の専門的な司法書士に限られます。
裁判業務は一部、登記と相続が主軸
このように、司法書士にも裁判業務の幅はありますが、実務の中心はあくまで次の3つです:
-
登記(不動産登記・商業登記)
-
相続(遺言、信託、後見など)
-
債務整理(簡易裁判所での手続き含む)
裁判業務も選択肢のひとつではありますが、司法書士の本領はやはり予防法務や手続きサポートにあります。
その他の仕事
帰化申請など
司法書士の業務には、登記や相続、裁判関連以外にも、いくつかの業務があります。そのひとつが「帰化申請」のサポートです。
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための手続きです。法務局に対して多くの書類を提出し、一定の条件を満たす必要があるため、専門的な知識や正確な書類作成が求められます。
司法書士は、申請書類の作成支援や、必要書類の整備、申請の流れに関するアドバイスなどを通じて、この手続きをサポートすることができます。
ただし、この分野に特化して活動している司法書士は比較的少なく、多くの事務所では登記や相続関連業務が中心となっています。そのため、帰化申請に力を入れている司法書士事務所は一部に限られています。
また、帰化申請業務は行政書士の主要分野でもあるため、競合となる場面もあり、司法書士が積極的に取り組むケースは限られがちです。
その他の業務の可能性
この他にも、司法書士には以下のような業務分野があります:
-
各種契約書の作成支援
-
成年後見制度の申立書作成
-
法務局への供託手続き
-
法人設立の支援
ただし、こうした業務も事務所によって対応範囲が異なります。
司法書士は幅広い法的手続きのスペシャリストである一方で、実際の業務内容は、各司法書士の専門分野や事務所の方針によって変わってくるのが実情です。
まとめ:最近の業界事情
登記の仕事はバブル期がピークでした。その後バブルが崩壊すると不良債権が増えました。銀行が、お金を貸したのに回収できない。そうなると、債権(回収できる権利)を売ることになります。こういった債権に関する仕事が増えました。
債務整理は、銀行がお金を貸して借りる人がいる以上は絶対になくなりません。従って、債務整理のマーケットも残っていくはずです。
また今後は、法人と個人事務所に分かれていくと思います。
法人であれば、総合的に何でも対応する事務所になっていくはずです。個人であれば、専門分野を極めた事務所にしていく必要があると思います。この地域の登記であればこの事務所、といったように専門性を極めるべきです。
司法書士は、みなさん結構仕事があって、食べていけないという人はいないですね。この資格があれば、困ることは少ないです。
景気がいい時は登記の仕事が多く、景気が悪くなると債務整理が多くなるといった感じで、仕事が無くなることはないでしょう。景気によって求められる仕事は変わりますが、いい時も悪い時もそれぞれの仕事があるので、恵まれている仕事と言えると思います。

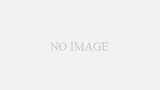
コメント