司法書士試験に合格すると、いよいよ実務家としてのスタートが見えてきます。ただし、合格したからといってすぐに働けるわけではなく、就職活動や各種研修、さらには「認定考査」など、乗り越えるべきステップがいくつもあります。
この記事では、合格後に待っている流れや、それぞれの研修内容、そして実際にかかる費用について詳しく解説します。合格後に「何から始めればいいの?」「いくらかかるの?」と不安になる方のために、体験をもとにしたリアルな情報をお届けします。
司法書士試験に合格した後の流れ
司法書士試験に合格した後の流れは、大まかに以下のようになっています。
口述試験に合格⇒就職活動⇒新人研修⇒特別講習⇒配属研修⇒認定考査
もう少し詳しく見ていきましょう。
就職活動いつから始めるべき?
司法書士試験に合格すると、多くの人がまずはどこかの事務所に就職しようと考えるでしょう。そこで気になるのが「就職活動はいつから始めればいいのか?」という点です。
人によって意見はさまざまですが、「早ければ早いほどいい」という声もよく聞かれます。ただ、私個人の考えとしては、そこまで急ぐ必要はないと思っています。
合格発表は11月にありますが、年内は少しゆっくり過ごして、就職活動は年明けから本格的に始めても十分間に合います。ただし、その間にしっかり情報収集だけはしておきましょう。
11月頃には、大手の司法書士法人が「今だけ募集しています」「早めに就職先を決めたほうがいいですよ」といったアピールをしてくることもあります。しかし、実際にはそのような事務所も通年で人材を募集していることが多いのです。焦って決める必要はありません。
一方で、個人の司法書士事務所は募集自体が限られていて、狭き門となることもあります。ただ、将来的に独立を目指している方にとっては、個人事務所のほうが経験の幅を広げやすく、登記の最初から最後まで任せてもらえる環境が整っている場合も多いです。
いずれにせよ、事務所選びは今後のキャリアを大きく左右します。「どんな働き方をしたいか」「自分に合った環境はどこか」をよく考え、焦らずじっくりと探すことをおすすめします。
司法書士の就職市場は基本的に売り手市場です。必要以上に急いで就職先を決めるより、自分にとって最適な環境を見極めることが大切です。
研修について
司法書士試験に合格した後は、さまざまな研修に参加することになります。それぞれの研修には目的があり、今後のキャリアに役立つ重要な機会です。しっかりと意識を持って取り組みましょう。
新人研修
合格者を対象に「新人研修」が実施されます。ここでは、同期との出会いが最大の魅力です。司法書士としてのスタートラインに立つ仲間と交流できる貴重な機会なので、ぜひ積極的に参加しましょう。
この研修は一生に一度だけ。今後の仕事でも情報交換や相談ができる、心強い人脈が築けます。研修内容そのものももちろん重要ですが、同期とのつながりは何よりの財産になります。
特別研修
簡易裁判所での訴訟代理権を得るためには、「認定考査」という試験を受ける必要があります。この認定考査を受験するためには、事前に「特別研修」の受講が必須です。
この特別研修も、多くの合格者が受講しています。実際に訴訟代理を業務にするかどうかに関わらず、将来的な選択肢を広げるためにも、受けておくことをおすすめします。
配属研修
「配属研修」は、実際の司法書士事務所に一定期間配属され、実務を学ぶ制度です。参加は任意ですが、多くの人が受講しています。期間は通常4週間程度で、各都道府県の司法書士会が主催します。
配属先の事務所は自分では選べません。大手事務所から個人事務所まで、規模や雰囲気はさまざま。丁寧に指導してくれるところもあれば、業務が忙しくて自分から積極的に学ばないと得るものが少ないケースもあります。
そのため、どのような環境に配属されても、「自分は何を学びたいのか」という目的意識を持って取り組むことが大切です。環境が厳しくても、現場を体験すること自体が大きな学びになります。
司法書士会によっては、配属先に対する希望や要望をある程度聞いてくれる場合もあります。事前に相談してみるのも良いでしょう。
認定考査について
認定考査は、司法書士として業務の幅を広げるために、ぜひ受けておきたい試験です。試験は司法書士試験に合格した翌年の秋ごろに実施され、多くの方が勤務と並行しながら勉強しています。
合格率は年によって差がありますが、おおむね40〜70%程度です。決して簡単ではないため、しっかりと対策を取る必要があります。司法書士試験を終えたばかりで、勉強習慣がまだ身についているうちに受験するのが最も効率的です。後回しにすると、なかなか勉強のペースがつかめなくなります。
また、認定考査に合格しないと、簡易裁判所での訴訟代理業務を行うことができません。近年ではこの業務のニーズも増えており、実務での活躍の場を広げるためにも取得しておくべき資格です。
なお、合格発表は名前が公表されるため、同期の中で誰が合格したのかが一目でわかります。落ちた場合は少し気まずい思いをすることもあるので、しっかり準備をして臨みましょう。
司法書士試験に受かってからかかるお金
まとめ
司法書士試験に合格してからは、就職活動や研修、認定考査といった一連のステップを経て、ようやく実務家としての第一歩を踏み出せます。
それぞれの段階には費用も時間もかかりますが、事前に流れを把握しておけば、慌てずに対応できます。特に、就職先や配属研修先の選び方、研修への取り組み方はその後のキャリアに大きな影響を与えるため、しっかりと準備を進めましょう。
合格後も油断せず、次のステージに向けた行動を着実に進めていくことが大切です。

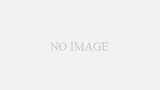
コメント