司法書士になろうかと考えている方や興味のある方は、司法書士はAIでなくなるという予想を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これは2015年に野村総研とオックス不フォード大学の共同研究で、士業は10年~20年後に人工知能(AI)に代替される可能性が高い、と発表された件です。司法書士の代替可能性は78.0%とされました。
「合格率5%の難関試験を通って仕事をしているのに、仕事がなくなるの?それでは意味ないので、やめた!」と思う方もいるかもしれません。
果たしてこの予想はほんとなのでしょうか?
そこで、AIで司法書士は消えるのか?生き残るためにはどうすればいいのか?ということについて考えてみたいと思います
そもそもAIとは?
そもそもAIとは何か?
実は、ホントの意味のAI(人工知能)はまだ開発されていません。
最近話題になったりしている「AIがチェスで人間に勝った」といったものは、人間の知能の一部機能だけに特化した「AI技術」です。チェスの場合は、チェスを行うということだけに特化した技術を使っているということです。人間の脳はチェスだけをやってるわけではないので、あくまでもチェスに特化したAI技術での話なんです。
ただややこしいので、ここではAI技術のことをAIと表記していきます。
AIが得意なことは、厳格なルールの範囲内で瞬時に適切な答えを出すことです。
司法書士のメイン業務である登記申請などは、ガチガチにルールが決まっているものです。細かいルールは、人間は忘れますがAIは忘れません。なのでこういった業務はAIの得意分野となります。そういったことから、司法書士の仕事は消えるのではないかと言われています。
ただ、AIは人間の言葉を理解できないということがあります。
例えば、Siriに「近所のイタリアンレストランは?」と聞いた時と「近所のイタリアン以外のレストランは?」と聞いた時は、同じ答えが返ってきます。なぜこうなるかというと、Siriは「近所」「イタリアン」という単語だけを拾って検索するからなんです。
また、「先日、岡山と広島に行ってきた」と「先日、岡田と広島に行ってきた」という文章の違いはAIには分からないそうです。AIは、「岡山」は地名で、「岡田」は人名だということが分からないからだそうです。
つまりまだAIは、人間の知能並みには人間の言葉を理解できないということなんです。
AIの研究の元のデータに問題あり?
野村総研の研究では、どういうプロセスで「司法書士はAIでなくなる」と結論付けたのでしょうか?
これを判断する元になったデータがあるそうで、それは「601種の職業従事者は必要なスキル等についてWEBアンケートで自己申告」したものだそうです。
ということは、
- 司法書士の仕事がどういうものかを具体的に調べたのではなく、機械的に計算しただけ。
- 司法書士業務のどの部分がAIで代替可能かを発表したわけではない。
- そもそも大元となるデータが自己申告のアンケートに基づくものなので、正確性に欠けると思われる。
ということで、AIに取って代わられるという予想は大雑把なもので、私はあくまでも仮設の域を出ないと思います。
司法書士業務の本質とは?
それでは司法書士業務の本質とは一体どういうものでしょうか?
たとえば、「父から私に不動産を生前贈与したい」という相談があった場合
- 本当に「生前贈与」なのか?
相談の半数は財産分与や代物弁済と混同している - 目的と手段は一致しているか?
節税が目的なら遺言の方が良い場合も - 本人意思確認
- 登記申請
- 税理士に繋ぐ
生前贈与として相談された場合でも、よく話を聞いてみると財産分与だったりすることがあります。一般の方は、その辺はよく理解できていないことが多いんですね。そこで、本来の目的を聞き取って、一番いい方法を提案することになります。相談者の背景によって、似たような相談でも最適な方法は変わってきたりするので、総合的な判断が必要となります。
このように状況を踏まえた判断は、人間でないとできないことです。
この中でAIが代われる業務は何でしょうか?
4の登記申請だけですね。
AIは言葉を理解できないので、コンサル的な仕事はできません。コンサル的な仕事とは
- 状況を分析し感情を組みとる
- 課題を整理する
- 方向性を提案する
- 意思決定を支援する
- 相手が理解していることを確認しながら説明をする
これらがコンサル的な仕事で、司法書士は書類だけ作っているのではなく、むしろこういったコンサル的な仕事がメインなんです。
登記申請は司法書士の業務の2割ほどなので、AIは2割程度しか変わることができないということになります。
ということで、私は司法書士の代替可能性は78.0%という数字は、現実とかけ離れていると思います。
士業(司法書士)のAI化は後回し?
AI化が進んでいくとなった時、AI化には費用がかかるので市場が大きく費用対効果が高いところから始まっていくと思われます。
市場規模が大きいところと言うと、運輸や金融あたりでしょう。
そうなると、職業人口が少ない士業・司法書士は後回しになると予想されます。したがってあと10~15年くらいはAI化されないのではないでしょうか。
まとめ・AIに仕事を取られないために
「AIで司法書士の仕事がなくなる」というのは現実離れしていると思われます。おそらくここ15年前後は実現しないでしょう。
ただ、AIはどんどん進化しているので20~30年後は分からないです。人間の脳と同じ構造を持つニューロコンピュータが開発されれば、どうなるかはわかりません。
また、司法書士の仕事をただの「手続きや」としてやっていてコンサル業をやっていないのであれば、前項でも書いているようにAIに仕事を取られるかもしれません。
司法書士が生き残るためには
- コンサルティングの要素の強化
- 資格に依存しない、あなただからできること、依頼者が求める「プラスα」を作り伝える
- 信頼の獲得。人間にしかできないこと、あなたが何ができて、どういう人間なのかを伝える
こういった姿勢で業務に取り組んでいくことが必要で、それができていればAI化が進んでも仕事を取られることは無いのではと思います。

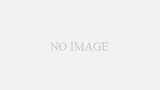
コメント