司法書士試験は難関資格のひとつとされ、予備校に通わなければ合格できないと思われがちです。しかし、私は予備校を使わず、独学で合格を勝ち取ることができました。もちろん簡単ではありませんでしたが、正しい教材選びと勉強法を徹底すれば、独学でも十分に合格を狙えます。
本記事では、私が実際に使ったおすすめのテキストや、効率的な勉強法、独学を成功させるためのポイントを、実体験をもとにわかりやすくご紹介します。
独学で合格する勉強法とは?
「独学で最短合格を目指したい」「教材はできるだけ少なくしたい」「分厚い過去問集は使いたくない」——そんな方に向けた、実際に独学で司法書士試験に合格した私の勉強法をご紹介します。
結論から言うと、私は『オートマテキスト』をメイン教材として使用し、独学で合格しました。過去には、TACの山本浩司先生による「オートマチック講座」のDVDも活用していました。
仮に予備校に通ったとしても、合格のカギとなるのは「自学自習」、つまり独学です。スポーツでも、良いコーチに習うだけでなく、自主練習の時間が上達を左右しますよね。それと同じで、司法書士試験も「どれだけ質の高い独学ができるか」が合否を分けるのです。予備校に通っても短期合格できない人が多いのは、この独学力に差があるからだと思います。
だからこそ、講義を聞くこと以上に、自分に合ったテキストや問題集を使って、自分でしっかり勉強を進めることが大切です。それが、最短合格への近道です。
ここからは、私が実際に使った教材についてご紹介します。ですがその中身は、司法書士試験の常識を覆すかもしれません。なぜなら、多くの受験生が「必須」とする過去問集や登記六法、判例六法を一切使っていないからです。
お勧めはオートマシステム
私が使っていたテキストは、『オートマシステム』シリーズです。
「オートマ」は非常にわかりやすく、独学で合格する人が増えたのも、この教材のおかげだと感じています。特に民法のテキストは語り口調で書かれており、まるで山本浩司先生の講義を読んでいるような感覚で学べます。そのため、無理に予備校の講義を聞くよりも、「オートマ」を読んだ方が理解しやすいと感じる方も多いでしょう。
「オートマ」の大きな特長は、条文や制度の“趣旨”や“理由”をしっかり解説してくれている点です。これにより、丸暗記ではなく「なぜそうなるのか」を理解しながら覚えることができます。こうした理解型の学習は、記憶が定着しやすく、長期間にわたって知識を保てるのが強みです。
また、趣旨や理由を押さえて学ぶことで、見たことのない応用問題にも対応できる“考える力”が養われます。条文の暗記だけでは太刀打ちできない未知の問題も、背景を理解していれば、論理的に答えを導き出すことが可能です。これは本試験で大きな武器になります。
このように、「オートマシステム」は単なる暗記型の教材とは異なり、理解と応用力を重視した完成度の高いテキストです。司法書士試験を独学で目指す方には、特におすすめできる一冊です。
オートマで足りるのか?
オートマのイマイチなところ
どんなに優れた教材でも、気になる点はあるものです。ここでは、『オートマシステム』の気になった部分も正直にお伝えしておきます。
まず私が感じたのは、「誤植の多さ」です。最近は改善されているかもしれませんが、私が勉強していた当時は、細かな誤植がちらほら見られました。ただし、『オートマ』は毎年内容の見直しと改訂を続けていて、誤植についてもTAC出版の公式サイトで正誤表がすぐに公開されるため、それほど大きな問題にはなりませんでした。購入後は正誤表の確認を習慣づけるとよいでしょう。
もう一つ、よく指摘されるのは「語り口調のクセ」です。『オートマ』は講義風の語り口で書かれており、人によっては読みづらく感じるかもしれません。私はむしろ親しみやすくて気に入りましたが、合う・合わないがあるのは事実です。購入前に一度中身を立ち読みしたり、サンプルを読んだりして、自分に合うかどうかを確かめるのをおすすめします。
とはいえ、自分にフィットすると思えた方にとっては、『オートマ』は非常に頼れる教材になるはずです。合うと感じたなら、ぜひ最後まで信じて取り組んでみてください。
その他のおすすめのテキスト
オートマで足りないところを補うため、以下のテキストも使っていました。
デュアルコア商法
次にご紹介するのは、『デュアルコア商法』です。
私はこの教材を、狭義の商法(商法総則・商行為法)の学習に活用していました。
そもそも司法書士試験における「商法」という科目は、実際には「商法」と「会社法」の2つの法律が出題範囲に含まれています。そのうち「商法(広義)」の中でも、特に「商法」と呼ばれる部分の学習に、この『デュアルコア商法』を使っていました。
というのも、私が勉強していた当時の『オートマ』では、商法についての解説が非常に簡略で、会社法がメインになっており、商法部分は“おまけ程度”の扱いだったからです。そのため、より丁寧な解説が欲しいと感じ、『デュアルコア商法』を選びました。
この教材は講義形式で進められており、趣旨や理由づけが丁寧にされているだけでなく、図表も多く使われているため、理解や記憶の定着に役立ちました。さらに、巻末には過去問も収録されており、実戦的な学習にも活用できます。
ただし、法改正が頻繁にある分野でもあるため、購入前には最新版であるかどうかをしっかり確認することをおすすめします。
オートマシステムプレミアム憲法
次にご紹介するのは、『オートシステムプレミア憲法』です。
憲法分野に関しては、『オートマ』テキストだけでは十分な自信が持てなかったため、特に判例部分の学習に『オートシステムプレミア憲法』を活用しました。憲法の人権問題は、判例をしっかり理解しているかどうかで解ける問題があると思ったからです。
『オートシステムプレミア憲法』では、判例のみを重点的に学習しました。他の基本的な内容は『オートマ』テキストと重複する部分もあることと、それ以上手を広げる余裕が無かったからです。時間やリソースに制約がある中で、憲法全体に手を広げすぎず、重要な判例のみをしっかりと固めることができたと思います。
憲法は深い内容を持つ科目であり、点数を取るのが難しいと感じる受験生も多いため、判例にフォーカスした学習方法が、効率的な対策となると思います。
新でるトコ一問一答
最後にご紹介するのは、『新でるトコ一問一答』です。
この問題集は、『オートマテキスト』の補助教材として、知識の整理やアウトプットのために使用していました。特に優れている点は、司法書士試験で実際に問われる重要論点に絞って、一問一答形式で効率よく学べるところです。
全4冊で試験範囲のすべてを網羅しており、しかも解説は基本的に1~2行で簡潔にまとまっているため、テンポよく学習を進めることができます。忙しい方でも短時間で一通り学習を回せるのは大きなメリットです。
私は過去問集は使わず、この『でるトコ』を徹底的に繰り返しました。『オートマ』との相性も非常によく、組み合わせて使うことで理解が深まり、効率的な学習が可能になります。特に独学での勉強を考えている方には、強くおすすめできる教材です。
オートマシステム記述式
ここからは、司法書士試験の記述式対策に使用した教材をご紹介します。
私がもっとも活用したのが『オートマシステム記述式』です。
特に「基本の部」を何度も繰り返し解きました。記述式の基礎をしっかり固めたい方には、この「基本の部」だけでも十分な実力が身につくと感じています。ちなみに「応用の部」は難易度が高く、私は取り組みませんでしたが、基本を押さえるだけでも十分対応可能でした。
この教材の大きな強みは、さまざまな問題パターンに対応できる“型”が自然と身につく点です。つまり、記述式で問われる論点を体系的に理解し、柔軟に応用できるようになるのです。
記述式対策として、何をやればいいか迷っている方は、まずこの『オートマシステム記述式(基本の部)』から始めてみることをおすすめします。
六法について
六法は、テキスト・過去問と並んで「勉強の三種の神器」と言われることもあり、「使って当然」と思われがちです。法律の原点である条文が収録されているため、重要な教材であることに間違いはありません。
ただ、私自身は「ポケット六法」を持ってはいたものの、実際にはほとんど使いませんでした。その理由は、条文の内容やその趣旨、わかりやすい解釈がすでに『オートマシステム』にしっかり盛り込まれていたからです。必要な情報はオートマで事足りたため、六法を引く機会は自然と減っていきました。結果的に、「オートマ」と補助的に「ポケット六法」を使うだけで、十分合格に必要な力は身につけられました。
過去問題集について
「過去問はやらなかったのですか?」とよく聞かれます。結論から言うと、私は本格的な過去問集には取り組みませんでした。
理由のひとつは、単純に手が回らなかったからです。買い揃えたのは『オートマ過去問集』で、問題が厳選されており、解説も簡潔で回しやすそうだと感じたからです。
実際には、『オートマテキスト』と「新でるトコ一問一答」を繰り返し使うだけでも、十分なアウトプットと知識の整理ができたと実感しています。過去問に手を広げる時間がなかったことを後悔することはありませんでした。
まとめ
おそらくあなたが考えている司法書士試験を合格するためのレベルは、私が思うレベルとかなり違うと思います。
あなたが思う合格レベルは、本試験に出てくるほとんどの問題を瞬時に解いて正解できるというイメージでしょう。ですがこの合格レベルは、本来の合格レベルとはかけ離れていて、ここまでいくには際限なく勉強しなければいけません。
大事なのは、オートマでもなんでも、自分にあった教材を繰り返して完璧に近づけることです。そうすれば完璧になれなくても合格します。
選択肢の60%を正解すれば合格するので、分からない問題は消去法で回答してもいいんです。
自分を合格レベルまで持っていくには、やることを絞って繰り返すこと。司法書士試験の勉強範囲は膨大で覚えることが多く大変ですが、やることを絞ればできる気がしてくるのではないでしょうか。いろいろな教材に中途半端に手を出すのではなく、しぼった教材を繰り返しやって完璧を目指すことです。
あなたの司法書士試験合格のための参考にしてください。

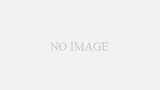
コメント